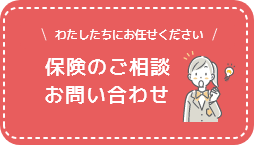死亡保険の種類と使い方を徹底解説!賢い活用法とは?
1. 死亡保険とは?
死亡保険とは、契約者が亡くなった際に、遺族などの受取人に保険金が支払われる生命保険の一種です。主に以下の目的で加入されます。
- 家族の生活費の補填
- 住宅ローンや借金の返済
- 葬儀費用の準備
- 子どもの教育資金確保
では、具体的にどのような種類があるのか見ていきましょう。
2. 死亡保険の主な種類
死亡保険は大きく分けて「定期保険」「終身保険」「収入保障保険」の3種類があります。それぞれの特徴を詳しく解説します。
① 定期保険(掛け捨て型)
特徴
- 保険期間が決まっており、満期を迎えると保障は終了。
- 掛け捨てのため、満期時にお金は戻らない。
- 保険料が比較的安く、大きな保障を得やすい。
向いている人
✅ 子どもが独立するまでの間、一定額の保障が欲しい人
✅ 保険料を抑えつつ、高額の保障を確保したい人
活用例
- 30歳で結婚し、子どもが成人するまでの20年間、3000万円の保障を確保する。
- 住宅ローンを組んだ際に、ローン返済期間中のみ保障を設定する。
② 終身保険(貯蓄型)
特徴
- 一生涯の保障が続く。
- 解約返戻金があり、資産形成としても活用できる。
- 定期保険に比べると保険料が高め。
向いている人
✅ 一生涯の保障を確保したい人
✅ 老後の資産形成を兼ねたい人
活用例
- 終身保険を活用し、将来の葬儀費用を準備する。
- 途中で解約して老後資金や子どもの結婚資金に活用する。
③ 収入保障保険
特徴
- 被保険者が亡くなると、毎月または毎年、年金のように保険金が支払われる。
- 保障期間が経過すると、支払われる保険金総額は減っていく(定額で受け取るプランもあり)。
- 保険料が割安で、無駄なく必要な保障を確保できる。
向いている人
✅ 遺族の生活費として安定した収入を確保したい人
✅ まとまった保険金の管理が難しいと感じる人
活用例
- 子どもが成人するまでの間、毎月15万円ずつ受け取れるように設定する。
- 配偶者が高齢になった際の生活費として、一定期間、年金のように受け取る。
3. 死亡保険の選び方
① 必要な保障額を決める
死亡保険に入る際には、必要な保障額を決めることが重要です。以下のようなポイントを考慮しましょう。
✔️ 葬儀費用:150万〜300万円
✔️ 住宅ローン残高:団信(団体信用生命保険)でカバーできるか確認
✔️ 子どもの教育費:大学進学を考えるなら最低500万円~1000万円
✔️ 配偶者の生活費:配偶者の収入や年金を考慮
② 保険料とのバランスを考える
必要な保障額が決まったら、保険料とバランスを取りながら選ぶことが大切です。無理のない範囲で継続できる保険を選びましょう。
③ 保険の見直しを定期的に行う
ライフステージによって必要な保障は変わります。例えば…
🔹 結婚・子どもの誕生 → 保障額を増やす
🔹 子どもの独立 → 保障額を減らす
🔹 老後 → 終身保険や資産運用を考える
4. 死亡保険の賢い活用法
① 終身保険を活用して相続対策
終身保険の死亡保険金は、**「500万円 × 法定相続人の数」**まで非課税となるため、相続税対策として活用できます。
② 保険金の受け取り方を工夫する
一括で受け取ると無駄遣いしやすい場合、**年金方式(収入保障型)**にすることで、計画的にお金を受け取ることができます。
③ 会社員は「団体保険」も検討
勤務先で団体生命保険がある場合、個人で加入するよりも割安で同等の保障を得られることがあります。