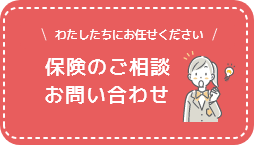医療保険をやめても大丈夫?退職後の医療費と保障の考え方
働いている間は給与や会社の福利厚生で医療費がカバーされる場合も多いですが、退職後は自分で医療保障を見直す必要があります。特に定年退職を迎えた後は、公的医療保険や制度を上手に活用しつつ、民間医療保険を続けるか解約するかを検討するタイミングです。今回は、退職後の医療費や保障をどう考えるべきかについて解説します。
1. 退職後に適用される「公的医療保険」と「高額療養費制度」
まず、退職後に適用される公的医療保険の仕組みについて理解しておきましょう。65歳までは、退職後でも国民健康保険や元の健康保険の「任意継続」に加入できますが、75歳以降は原則として「後期高齢者医療保険制度」に移行します。
後期高齢者医療保険制度では、自己負担が1割または2割(収入によって異なる)となるため、退職後は現役時代に比べて医療費の自己負担が減少するケースが多いです。また、日本には高額療養費制度もあり、1か月の医療費が一定額を超えると超過分をカバーしてもらえるため、医療費が高額になった場合でも負担が軽くなります。
2. 退職後に医療保険を継続するメリット
退職後に民間の医療保険を継続するメリットもいくつかあります。特に、がんや心臓病などの高額治療費がかかる病気に備えたい場合は、医療保険でしっかり保障を持っておくと安心です。高額療養費制度があるとはいえ、差額ベッド代や交通費などは自己負担になるため、入院一時金や先進医療特約が付いた医療保険があると、予想外の出費に対応しやすくなります。
また、年齢を重ねてから新しい保険に入ると、保険料が高くなる傾向があるため、若いうちに加入した医療保険を退職後も継続することで、低い保険料で保障を維持できる点もメリットです。
3. 医療保険を解約する選択肢もある?
一方で、後期高齢者医療保険制度や高額療養費制度を考えると、「医療保険は不要では?」と感じる方もいるかもしれません。実際に、医療費の負担割合が1割や2割に軽減される後期高齢者医療保険制度に移行すると、自己負担が大幅に減るため、民間医療保険の必要性が薄れるケースもあります。
また、高齢期には貯蓄がある程度蓄えられていることも多く、貯蓄でカバーできる範囲なら医療保険を解約して保険料の支出を抑えるという選択も可能です。特に、終身払いで保険料の支払いが継続する場合、解約して支出を抑えることで、生活資金を無駄なく管理できるかもしれません。
4. 解約する場合に注意すべきポイント
医療保険の解約を検討する際は、現在の保障内容と、退職後に予想される医療費を考慮して慎重に判断することが大切です。たとえば、がんや持病があり将来にわたって治療費がかかると予想される場合は、医療保険を残しておく方が安心でしょう。
また、今後医療技術が進み、保険適用外の治療が増えた場合を考えると、先進医療特約などが付いていると、最新の医療技術へのアクセスがしやすくなることも見逃せません。退職後の生活資金や家族構成、将来の健康リスクも考慮した上で、解約するか継続するかを決めましょう。
5. まとめ:退職後の医療費を見据えた賢い選択を
退職後の医療保険の継続は、公的医療保険と民間保険のバランスを見極めることが重要です。高齢期には公的医療保険制度が充実しているため、自己負担が大幅に軽減される一方で、特定の治療費や保障が必要な場合には、民間医療保険の継続も検討の価値があります。
自分の健康状態や生活資金、家族の状況を見据えた上で、医療保険を継続するか解約するかを決め、老後の生活に合わせた最適な医療保障を備えていきましょう。退職後に安心して生活を楽しむためにも、今一度医療保険を見直してみてはいかがでしょうか?